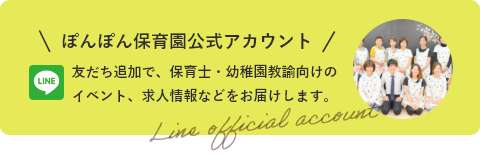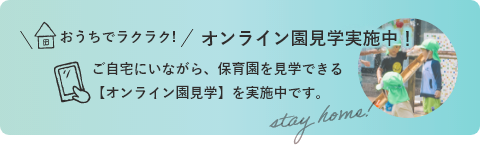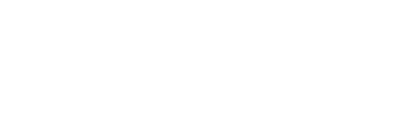 blog
blog
乳幼児は、自分の感情を保育者にどう扱われたかで、感情の扱い方を学ぶ
ぽんぽん先生ブログ先日、助産師さんや看護師さんなどに向けてお話をさせていただく機会がありました。産前産後の妊産婦支援は、感情を扱うことや計画が思い通りには進まず、その都度、柔軟な対応が求められる点など、乳幼児保育と共通する部分が多く見られます。その時の内容の一部ですが、日々の保育のご参考になれば幸いです。
【大脳辺縁系と前頭前野】
大脳辺縁系と前頭前野の成長についてですが、大脳辺縁系は、生まれてすぐから活発に働きます。喜怒哀楽のといった感情の火種は赤ちゃんでもしっかり持っています。
それに対して、その感情をコントロールする役割を持つ前頭前野はとてもゆっくり成長し、20代半ば頃にようやく完成すると言われています。
前頭前野の成長を、少し細かく、順を追って確認していきましょう。
感情を爆発させる2歳~3歳頃のイヤイヤ期。まだこの頃は前頭前野が担う抑制の力は弱く、感情のコントロールが難しい。
4~6歳になると、少しずつ「待つ」「譲る」といった行動ができるようになる。とはいえ、まだ未熟で気分に左右されやすい。
小学生(7~12歳)になると、学習や集団生活を通して、ルールを守って感情を抑えたりする力が伸びます。
思春期(10代後半~20代前半)は、ホルモンの影響で感情が揺れ動きますが、経験と前頭前野の成熟により抑制の力は徐々に落ち着いてきます。
つまり、乳幼児期に「うまく感情がコントールできない」のは当たり前で、「保育者側の環境設定」や「乳幼児に心を寄せてそばにいること」が大事になるのです。その行動が、乳児の心を強く育み、自己肯定感に繋がっていきます。そのエビデンスも出ています。
こうした成長の過程を知らないと、保育者は、子どもを“変えよう”としたり、つい“幼い・障害”とラベルを貼ってしまうことがあります。
そうならないように、知っておくべき事項は
1.脳には感情の中枢(大脳辺縁系)と、それをコントロールする部分(前頭前野)がある
2.前頭前野はゆっくり発達する
3.乳幼児の教育は、子どもを“変える”のではなく、大人が理解して環境を整えることにウエイトを置くこと
【感情を扱うということ】
子どもの前頭前野は未熟だということをお伝えしましたが、要するに、保育者は大脳辺縁系という裸の感情に接しているということです。
感情は、大人においても、それを大切な人に理解してもらうことを、とても大事にしているのではないでしょうか。そして、その感情は、コントロールされず、共感されることを望んでいる人が多いはずです。それだけで人と人の関係は育まれていきます。
私たちはこの「ありのままの感情」をまず受け入れ、愛着を形成し、次のステップに入っていく必要があるのです。
子ども達は、自分の感情を保育者にどう扱われたかで、感情の扱い方を学んでいきます。律する保育者ではなく、手助けする保育者が心を強くしていることを忘れないようしていきましょう。
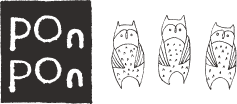

 よくあるご質問
よくあるご質問 採用情報
採用情報 お問い合わせ
お問い合わせ





 運営者情報
運営者情報 情報公開
情報公開 プライバシーポリシー
プライバシーポリシー